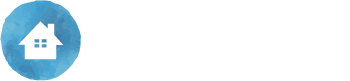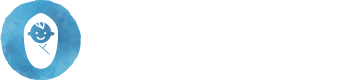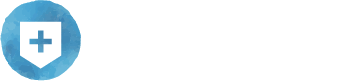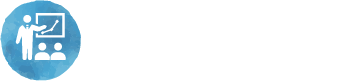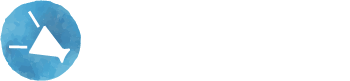洪水・土砂災害ハザードマップ よくある質問(Q&A)
目次
共通編
- 災害ハザードマップとはどのようなものですか?
- 災害ハザードマップの効果はどのようなものですか?
- 地震や洪水を防ぐことはできないのですか?
- 自助・共助・公助とは何ですか?
- 避難情報とは何ですか?また、どのように伝えられますか?
- 要配慮者とはどのような方ですか?
- 災害用伝言ダイヤル(171)とは何ですか?
- 近隣市町村との広域的な連携体制(防災協定など)はどのようになっていますか?
- 五泉市の防災備蓄品にはどのようなものがありますか?
- いつ避難すればいいのですか?
- 早期立ち退き避難が必要な区域とは何ですか?
- 避難路について教えてください。
- 避難時は車の利用を控えるべきですか?
- 避難所はどこにありますか?
洪水編
- 1,000年に1回の確率とは何ですか?
- 排水路や側溝などがあふれて起こる浸水も考慮されているのでしょうか?
- 浸水する場所に避難所がありますが、危険ではないですか?
- 浸水想定区域図はどうやって作成したのですか?
- 家屋倒壊等氾濫想定区域とは何ですか?
- 本当にこんな大きなエリアで浸水被害が発生するのですか?
- 洪水の時、周辺の安全な場所はどこですか?
- 浸水想定区域に指定されていないところは安全ですか?
- 洪水の時、どのような場合に避難情報が発令されますか?
- どれくらいの雨だと危険ですか?
- 小さな川などのはん濫は想定されていないのですか?
- 五泉市ではどんな対策を行っていますか?
土砂災害編
- 土砂災害とはどのようなものですか?
- 土砂災害はどれくらい起きているのですか?
- 土砂災害はいつ起きるのですか?
- 土砂災害の前兆現象とはどのようなものですか?
- 土砂災害警戒区域とは何ですか?
- 私の家が土砂災害警戒区域に入っていますが大丈夫ですか?
- 今まで何十年も土砂災害などは起こっていない箇所でも土砂災害は起こるのでしょうか?
回答
共通編
1.災害ハザードマップとはどのようなものですか?
災害ハザードマップとは、河川がはん濫した場合や山沿いで発生するがけ崩れなどの土砂災害が発生した場合に備えて、地域の住民の方々がいち早く安全な場所に避難できることを目的に、被害の想定される区域と被害の程度、さらに避難場所などの情報を地図上に明示したものです。
また、今回の災害ハザードマップは、水防法の改正に伴い、対象となる河川(阿賀野川、早出川、能代川等)の管理者である国・県が作成した、最大規模の降雨(1,000年に一度程度の確率)を想定した新たな洪水浸水想定区域を示しています。以前に作成した「五泉市防災マップ(平成18年度作成)」に比べて、浸水範囲が広く、浸水深が深くなっている可能性が高いので、再度確認してください。
さらに、土砂災害防止法に基づき県が指定した、土砂災害警戒区域及び土砂災害特区別警戒区域を種別ごとに色分けして表示しています。
これらのほか、普段から災害・防災について学べるよう、学習ページを充実させたハザードマップとなっています。
2.災害ハザードマップの効果はどのようなものですか?
- 前もって災害による被害を知ることができる。
- 普段から災害に対する危機意識を持つことができる。
- 何をすべきか、何が必要かが冷静に判断でき、いち早く避難することができる。
などの効果が考えられます。
例えば、福島県郡山市での1998年8月集中豪雨の事例では、避難情報が出てから避難を行うまでの時間が、災害ハザードマップを見たことがある人は、見たことがない人に比べて1時間も早いという報告もあります。
3.地震や洪水を防ぐことはできないのですか?
地震はいつどのような規模で発生するかの予測は困難です。
また、洪水についても、国や県、市が連携して堤防の整備などを推進していますが、近年多発する集中豪雨などの異常気象の状況を見ても、予想を超えるような雨が降ることが十分にありえます。
自然災害は人間の思うとおりにはならないことが多く、そのためにも災害に対する正しい知識を持ち、日頃から災害に備え、いざという時には正しい情報を聞いて速やかに避難することなどが重要です。
4.自助・共助・公助とは何ですか?
- 「自助」とは、家庭で日頃から災害に備えたり、災害時には事前に避難するなど、自分の身を自分で守ることを言います。
- 「共助」とは、地域の災害時要配慮者の避難に協力したり、地域の方々と消火活動を行うなど、周りの人たちと助け合うことを言います。
- 「公助」とは市役所や消防・警察による救助活動や支援物資の提供など、公的支援のことを言います。
災害時には、自助・共助・公助が互いに連携し一体となることで「減災」となり、被害を最小限にできるとともに、早期の復旧・復興につながるものとなります。
5.避難情報とは何ですか?
避難情報には、危険度に応じて「避難準備・高齢者等避難開始」「避難勧告」「避難指示(緊急)」の3つがあります。
・「避難準備・高齢者等避難開始」・・・お年寄りの方、体の不自由な方、小さな子供がいらっしゃる方など避難に時間のかかる方と、その避難を支援する方は避難を開始してください。それ以外の方も、気象情報に注意し、危険だと思ったら早めに避難してください。
・「避難勧告」・・・避難所など、より安全な場所に避難を開始してください。
・「避難指示(緊急)」・・・緊急に避難してください。外出することで命に危険が及ぶ状況の場合は屋内のより安全な場所に避難してください。
災害時、これらの避難情報は、市内に設置してある防災行政無線を使い最大音量で放送されるほか、登録式の五泉あんしんメールや緊急速報メール(エリアメール)、市ホームページを通じても発信しており、テレビやインターネットなどの各メディアなどへも情報提供しています。また、対象地区の町内会長への電話連絡や広報車による周知も行っています。
6.要配慮者とはどのような方ですか?
要配慮者とは、高齢者、障がい者、乳幼児、妊婦、外国人その他の特に配慮を要する方のことをいいます。要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生する恐れがある場合に、自ら避難することが困難であって、円滑で迅速な避難行動を取ることに特に支援を要する方を避難行動要支援者と言います。
7.災害用伝言ダイヤル(171)とは何ですか?
地震や大雨などの災害発生時には、特定の地域への電話連絡の殺到が予測されます。災害用伝言ダイヤルは、被災地への通話がかかりにくい状態(ふくそう状態)になった時、被災地内の家族、親戚、知人などと安否の確認や緊急連絡を取れるようにするものです。
全国どこからでもメッセージを録音・再生することができ、公衆電話や一般家庭のダイヤル・プッシュ回線の電話はもちろんのこと、携帯電話やPHSでも利用が可能です。
なお、同ダイヤルは災害時のみ利用が可能なサービスであり、災害伝言ダイヤルの提供開始や録音件数などはテレビ・ラジオ等でお知らせされます。
また、災害時にメッセージの伝言板の役割を果たすシステムとして、携帯電話やスマートフォンなどから安否情報の書き込みと閲覧ができる、災害用伝言板(web171)もあります。各携帯電話会社が提供するサービスで、このほかに、NTT東日本が提供し、パソコンでも使えるweb171もあります。
8.近隣市町村との広域的な連携体制(防災協定など)はどのようになっていますか?
防災協定については、近隣の11市町村と「相互援助協定」を締結しています。
新潟市、長岡市、三条市、新発田市、加茂市、燕市、阿賀野市、佐渡市、聖籠町、弥彦村、田上町
このほか、医療やライフライン等、病院や各業種の民間企業、協会等と防災協定を締結しています。
9.五泉市の防災備蓄品にはどのようなものがありますか?
毛布、飲料水、アルファ米、バランス栄養食、各種缶詰、哺乳瓶、災害時用トイレ、紙おむつ(成人用含む)、パーソナルテント、マスクなどを備蓄しています。
10.いつ避難すればいいのですか?
市から「避難準備・高齢者等避難開始」や「避難勧告」が発令されたら、災害ハザードマップを見て避難を始めてください。「避難指示(緊急)」が発令された場合は、直ちに避難を開始してください。また、テレビやラジオ、インターネットで得られる気象情報などの各種情報により自ら判断し、外が危険な場合は屋内の2階以上で安全な場所に避難するなど、自主的に安全な場所に事前に避難することが自分の身を守る最良の方法です。
11.早期立ち退き避難が必要な区域とは何ですか?
早期立ち退き避難が必要な区域には次のような区域が該当します。
・家屋倒壊等氾濫想定区域
・洪水浸水深で3.0m以上の区域
・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
洪水であれば、氾濫した洪水の流速が早く、氾濫流により木造の家屋が倒壊する恐れのある区域や、洪水の際に河岸が削られて(河岸浸食)、家屋が倒壊する恐れのある区域を、各河川の管理者が家屋倒壊等氾濫想定区域として設定しています。また、洪水浸水深で3.0m以上の区域は、建物の最上階も浸水する恐れがあることから、屋外への避難が必要になります。土砂災害では、土砂災害の恐れがある区域(土砂災害警戒区域)や、土砂災害により建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生じる恐れの区域(土砂災害特別警戒区域)を都道府県が指定し公示しています。
これらの区域は、洪水及び土砂災害が起きた際の危険度が高く、屋外への早期の立ち退きが必要な区域として明示しています。
12.避難路について教えてください
五泉市では、「避難路」の指定はしていません。
ただ、避難経路は、地域のみなさんが災害ハザードマップを参考にして、常日頃から確認し、実際に歩いて確認しておくと良いと思われます。
基準については、
- 山崩れや、がけ崩れ、建物倒壊及び落下物などによる危険が少ないこと。
- 最短時間で避難経路、避難目標地点、避難所に到着できること。
- 複数の迂回路が確保されていること。
- 河川沿いや、蓋のない側溝のある道路はできるだけ避けること。
などが上げられます。
13.避難時は車の利用を控えるべきですか?
洪水避難時の車の利用は、渋滞を引き起こし緊急車両の通行の妨げになるだけでなく、道路冠水により車の制御ができなくなり、脱出ができなくなることが多くあるため、利用には注意が必要です。
14.避難所はどこにありますか?
屋内避難所として46箇所あり、全ての施設が耐震対策済みとなっています。
避難所を開設する場合は、災害に応じて必要な避難所を開設し、その都度お知らせします。開設される避難所を確認して避難してください。また、屋外が浸水しているなど危険な場合には、屋内の2階以上で安全な場所に避難してください。
なお、避難所のうち、速やかに開設できるよう、あらかじめ職員体制を整えてある避難所を「基幹避難所」としており、避難所を開設する場合、災害の規模や状況に応じて必要な基幹避難所を優先的に開設することになります。基幹避難所は、川東小学校、橋田小学校、五泉中学校、五泉北中学校、図書館、村松体育館、さくらんど会館、大蒲原小学校の8カ所です。
洪水編
1.1,000年に1度程度の確率とは何ですか?
近年、これまで経験したことがないような大雨により、全国各地で洪水が発生しています。このことから、平成27年5月に水防法が改正され、対象となる河川(阿賀野川、早出川、能代川等)が想定し得る最大規模(1,000年に1度程度)の降雨により氾濫した場合の浸水想定区域図が、国や県などの河川管理者から示されました。この、想定し得る最大規模の降雨とは、過去の降雨データを解析して求めた降雨継続時間別、流域面積別に最大となる降雨量を用い、対象となる河川ごとに算定されたもので、年超過確立に換算すると概ね1/1,000程度になることから、1,000年に1度程度の確立としています。各河川の想定雨量、流域面積は以下の通りです。
| 河川名 | 計画雨量 | 想定雨量 | 流域面積 |
| 阿賀野川 | 想定最大規模 |
2日間総雨量382ミリメートル |
7,710平方キロメートル |
| 早出川 | 想定最大規模 |
2日間総雨量809ミリメートル |
258平方キロメートル |
| 能代川 | 想定最大規模 | 1日間総雨量731ミリメートル |
141.1平方キロメートル (支川 荻曽根川・滝谷川含む) |
| 牧川 | 計画規模 |
1日間総雨量298ミリメートル (平成23年新潟福島豪雨程度の降雨) |
18.35平方キロメートル |
※ 計画規模とは、想定最大規模が想定し得る最大の規模であるのに対し、洪水を防ぐための計画を策定する上で、将来的に被害が発生しないように整備するための目標とする規模のことで、牧川においては、想定最大規模の降雨による浸水想定区域図は示されておらず、平成23年の新潟福島豪雨程度の降雨を想定した浸水想定区域図を使用しています。
2.排水路や側溝などがあふれて起こる浸水も考慮されているのでしょうか?
されていません。一般に、大雨により阿賀野川や早出川、能代川などの河川の水があふれたり、堤防が破堤して起こるはん濫を「外水はん濫」といい、堤防内の排水路や側溝があふれたり、排水処理できずに、建物や土地・道路が浸水することを「内水はん濫」といいます。この災害ハザードマップで示されている浸水想定区域は、対象となる河川(阿賀野川、早出川、能代川等)の外水はん濫を対象としたものであり、内水はん濫については考慮されていません。
内水はん濫については、「五泉市浸水(内水)危険箇所図」を参考にしてください。
3.浸水する場所に避難所がありますが、危険ではないのですか?
浸水する危険のない場所へ避難するのが一番安全です。ただし、五泉市の場合は浸水しやすい低地の面積が広く、阿賀野川、早出川、能代川をはじめ洪水はん濫の危険のある河川が多くあります。
災害に応じて浸水する危険のない避難所を開設しますので、避難所の開設場所を確認して避難してください。また、屋外が浸水しているなど危険な場合には、屋内の2階以上で安全な場所に避難してください。
4.浸水想定区域図はどうやって作成したのですか?
設定した降雨において、堤防が決壊する場所や越水する場所を複数想定します。その箇所ごとにはん濫解析を行い、浸水する範囲や浸水深を予想します。各河川ごとに出されたこれらの予想結果を重ね合わせ、最も深くなる浸水深により浸水想定区域を設定し、色区分することによって作成されました。
参考
・2013年(平成25年)3月に新潟県が公表した「牧川洪水浸水想定区域データ」
・2016年(平成28年)5月に国土交通省が公表した「阿賀野川洪水浸水想定区域データ」
・2016年(平成28年)5月に国土交通省が公表した「早出川洪水浸水想定区域データ」
・2017年(平成29年)6月に新潟県が公表した「早出川洪水浸水想定区域データ」
・2017年(平成29年)6月に新潟県が公表した「能代川洪水浸水想定区域データ」(支川 荻曽根川・滝谷川含む)
5.家屋倒壊等氾濫想定区域とは何ですか?
河川が氾濫した場合に、氾濫した洪水の流速が早く、氾濫流により木造の家屋が倒壊する恐れのある区域や、洪水の際に河岸が削られて(河岸浸食)、家屋が倒壊する恐れのある区域を、各河川の管理者が家屋倒壊等氾濫想定区域として設定しています。家屋倒壊等氾濫想定区域は、家屋自体の倒壊の危険があることから、屋外への早期の立ち退きが必要な区域とされています。
6.本当にこんな大きなエリアで浸水被害が発生するのですか?
この浸水想定区域は、決壊すると被害が大きくなるような堤防を複数選んで、これらの堤防が同時に決壊した場合を想定してシミュレーションしたものです。
実際には、堤防が同時多発的に決壊することは、まず考えにくいですが、自分の家の近くの堤防が決壊した場合にどれくらいの影響があるかどうかの目安として判断いただければよいと思います。
7.洪水の時、周辺の安全な場所はどこですか?
市では屋内避難所を46箇所指定しています。災害ハザードマップの指定避難所一覧では、各避難所の浸水深を示しています。浸水区域内の避難所であっても、2階以上は浸水しない施設もあります。大雨の時には、雨の降り方や浸水の状況に注意し、危険を感じたら早めの避難を心がけましょう。
8.浸水想定区域に指定されていないところは安全ですか?
浸水想定区域は、対象となる河川(阿賀野川、早出川、能代川等)に、設定した降雨があった場合のはん濫状況を示したものです。想定外の降雨の際や、排水路や側溝などがあふれて起こる内水はん濫などにより、区域の外でも水害が発生することが考えられます。
9.洪水の時、どのような場合に避難情報が発令されますか?
洪水警報、大雨警報又は大雨特別警報が発令され、河川のはん濫、浸水等の恐れがあり、住民の生命に危険が及ぶと認められる時に発令されます。
10.どれくらいの雨だと危険ですか?
例えば、平成12年7月に能代川がはん濫した水害と、平成16年7月13日に三条市で甚大な被害のあった豪雨を比較すると、平成12年の集中豪雨では、村松観測所において3時間という短時間に雨が143ミリメートル降ったのに対し、平成16年の7.13水害では、時間をかけて多量の雨が降り、24時間の降水量は山間部で約300ミリメートルに達しました。また、平成23年7月新潟・福島豪雨では、早出川ダム観測所において、7月28日から30日の3日間で413ミリメートル、1時間あたり最大51ミリメートルの降雨がありました。
これらのことを踏まえ、具体的に何ミリ以上の降雨からが危険とは言えませんが、テレビ等を通じて気象台が発表する大雨注意報や警報は一つの目安になります。
11.小さな川などのはん濫は想定されていないのですか?
この災害ハザードマップは、阿賀野川、早出川、能代川(支川である荻曽根川、滝谷川を含む)、牧川がはん濫した場合の浸水想定区域を示しています。五泉市内には太田川など新潟県管理の河川がありますが、各河川におけるはん濫シミュレーションに基づく浸水想定区域図は策定されていません。五泉市も、小河川の浸水想定区域の指定がされた場合、洪水ハザードマップを改訂するなどして、市民のみなさんにお知らせしたいと考えています。
12.五泉市ではどんな対策を行っていますか?
市内を流れる市管理の河川や、水路の整備、雨水管の整備など、降った雨を速やかに排除する整備を実施しています。
しかし、最近頻発する予想を超えるような集中豪雨や、阿賀野川、早出川、能代川(支川である荻曽根川、滝谷川を含む)、牧川が破堤して全域が水没するような災害に対しては、五泉市の対策にも限界があることから、市民のみなさん一人ひとりの災害に対する備えが重要です。
土砂災害編
1.土砂災害とはどのようなものですか?
土砂災害とは、大雨や地震などが引き金となって、山やがけが崩れたり、水と混じり合った土や石が川から流れ出たりして、尊い命や財産が脅かされる自然災害です。主なものとして「がけ崩れ」「土石流」「地すべり」などがあります。
| がけ崩れ | 雨や地震などの影響によって、土地の抵抗力が弱まり、斜面が突然崩れ落ちる現象。崩れた土砂は、斜面の高さの2~3倍くらいの距離まで届くことがあります。地すべりと違うところは、前ぶれがあまりなく、突然起きること、スピードが速いことなどです。 |
| 土石流 | 山の斜面が崩れ、崩れた土や石などが雨水や川の水と一緒になって、一気に流れ出る現象。流れの速さは速度20~40キロメートルで、自転車並みのスピードです。中には巨大な岩が混じったものもあり、凄まじい勢いで家や田畑を押し流してしまいます。 |
| 地すべり | 比較的ゆるい斜面が広い範囲にわたって動く現象。家や田畑と一緒に大地がゆっくり動くこともありますが、突然一気に何十メートルも動くこともあります。そのため、たくさんの家や田畑などが巻き込まれてしまいます。 |
土砂災害の特徴として、長年起きていなくても、突然前触れも少なく突発的に発生したり、大きな破壊力で人命を奪うことが多くあります。また、降雨や地形、地質等の複数の要因が影響するため、精度の高い発生予測が困難なこと、同じ場所で繰り返し起こることは少ないことなども特徴の一つです。
2.土砂災害はどれくらい起きているのですか?
土砂災害は、全国で年間平均1,000件を超える件数が発生しています。
平成29年は全国で1,514件発生しており、そのうち新潟県で195件発生しています。県内での発生件数は全国で2番目に多く、平成19~28年までの過去10年の平均発生件数は77件で、こちらも全国で2番目に多い数字となっています。
3.土砂災害はいつ起きるのですか?
土砂災害の多くは、何日か続く長雨や、にわか雨などの急な強い雨の時に発生します。土砂災害の発生は、現地の地形や地質・植生・土地の利用状況など様々な要因によって左右されるため、発生箇所や時期を予測することは困難です。参考として、「1時間で20mm以上の雨」又は「連続した100mm以上の雨」を記録した場合は特に注意が必要です。
各地域の詳細な土砂災害の発生の危険度を新潟県が情報提供する、新潟県土砂災害警戒情報システムは、降雨時などに土砂災害の発生の可能性を確認するものとして有効です。
長雨や大雨の時、山やがけの近くでは、土砂災害発生の危険度や各種気象情報などを確認し、山やがけの様子に注意しながら早めの避難をお願いします。
4.土砂災害の前兆現象とはどのようなものですか?
土砂災害の前兆現象には、次のようなものがあります。
がけ崩れ
- がけから出ている水が濁っている。
- がけに亀裂が入る。
- 小石がぱらぱら落ちてくる。
土石流
- 山鳴りがする。
- 雨が降り続いているのに川の水位が下がる。
- 急に川の水が濁り、流木が混ざっている。
地すべり
- 地面に亀裂、段差ができる。
- 樹木が倒れる。
- 斜面から水がふき出す。
このような現象を見たり、聞いたら、避難勧告や避難指示(緊急)などに係わらず、直ちに地域の方と安全な場所に避難をしてください。特に、お年寄りや体の不自由な方へのご配慮をお願いします。
また、安全な場所に避難したのち、市役所へ連絡をお願いします。
5.土砂災害警戒区域とは何ですか?
平成13年4月に施行された「土砂災害防止法」に基づいて、新潟県ががけの高さや傾斜度など一定の基準に従って調査をし、市長の意見を聞いた上で知事が指定した、土砂災害の被害の恐れのある区域を「土砂災害警戒区域」(通称:イエローゾーン)といいます。また、中でも著しい被害の恐れのある区域を「土砂災害特別警戒区域」(通称:レッドゾーン)といいます。これらの区域は、土砂災害の危険度が高く、屋外への早期の立ち退きが必要な区域としてハザードマップでも明示しています。土砂災害特別警戒区域は、指定されると建築物の構造規制があるほか、県知事による建築物の移転等の勧告を行う場合があり、移転等の際の県による支援措置などもあります。
また、これらの指定された区域は、人家に影響を及ぼす区域を対象として指定されているため、指定されていない区域でも、特に山地や急斜面がある場所などは、大雨や地震の際は土砂災害が発生する可能性があるので注意が必要です。
新潟県土砂災害警戒区域等の指定状況及び基礎調査結果の公表状況(新潟県HP)
6.土砂災害危険個所が掲載されています。私の家が被害範囲に入っていますが、大丈夫ですか?
新潟県による基礎調査は、がけの高さや傾斜度など一定の基準に従って調査をしたものであり、今すぐに指定された場所が崩落したりするという意味ではなく、大雨や地震の時に注意していただくという意味で記載しています。大雨や地震の時のほか、少ない雨でも降り続いたときなどは、安全な場所から注意深く見て、異変や前兆があればすぐに避難してください。また、前兆現象があった場合は、市役所に連絡をお願いします。
7.今まで何十年も土砂災害などは起こっていない箇所でも土砂災害は起こるのでしょうか?
土砂災害は以前発生したことのある箇所で発生するばかりでなく、今までに発生したことがない箇所でも斜面の風化や異常気象などにより発生することがあります。土砂災害はひとたび発生すれば、逃げる暇もなく人命を奪う恐ろしい現象です。この現象は洪水と異なり発生の予測が困難で、土砂災害警戒区域は今のところ主に地形から判断するしかありません。
このため、平時から周辺のどこに危険箇所があるかを確認しておき、大雨や地震の際は、気象情報等の情報収集に努め、周辺の山やがけに異変がないかに注意して過去の経験に縛られすぎずに早めの行動をお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
最終更新日:2021年01月15日