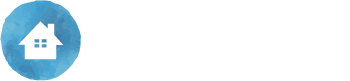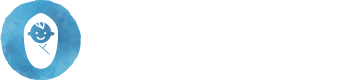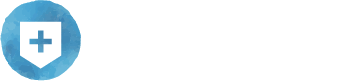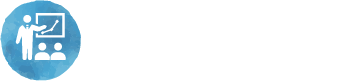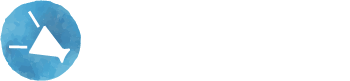国民健康保険(国保)
国民皆保険制度と国保
病気やけがをした時に、高額な医療費の負担を軽減してくれるのが、医療保険制度です。日本では、すべての国民が公的医療保険に加入することになっており、これを「国民皆保険制度」といいます。
公的医療保険の種類
| 制度(保険者) | 被保険者(加入者) |
| 国民健康保険(市町村、国民健康保険組合) | 農業従事者、自営業者、医師、建築業従事者 など |
| 健康保険(全国健康保険協会、健康保険組合) | 事業所の被用者及び日々雇用されている者 |
| 船員保険(全国健康保険協会) | 船員 |
| 共済組合(各共済組合) | 国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員 など |
| 後期高齢者医療制度(都道府県後期高齢者医療広域連合) | 75歳以上の者、もしくは65~74歳の一定障がい者 |
民間の生命保険や医療保険に加入していても、必ず公的医療保険に加入しなければなりません。
よって、五泉市に住所を有し、他の公的医療保険に加入できない人(生活保護対象者等を除く)は、必ず国民健康保険への加入の届出が必要になります。
※国民健康保険への加入・脱退(喪失)の届出は、事由が発生してから14日以内が原則です。14日を過ぎますと不利益が生じる場合がありますのでご注意ください。
加入について
加入する人
下記に該当しない人は国保に加入しなければなりません。
○自身あるいは家族の職場の健康保険・共済組合に加入している人
○後期高齢者医療制度に加入している人
○生活保護を受けている人
加入の手続き
次のような場合は、その事由が発生した日から14日以内に必ず市役所で手続きしてください。
国保への加入は自動では行われません。ご本人あるいは代理人の手続きが必要です。
届出が遅れると、国民健康保険税(保険税)の1回あたりの納付額が大きくなります。
| こんなとき | 必要なもの(共通) |
必要もの(個別) |
対象者が20歳~60歳未満の場合 |
| 五泉市に転入した時 |
・本人確認書類 ・マイナンバーカードまたは個人番号通知カード |
転出証明書 | なし |
| 職場などの健康保険をやめたとき | 資格喪失連絡票(PDFファイル:116.4KB)・任意継続喪失証明など |
年金手帳または基礎年金番号通知書 |
|
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
※注意※
医療機関を受診される際に、「重度障害者医療費受給者証」などを提示している場合は、一緒にお持ちください。国保の窓口後に担当の課へご案内いたします。
脱退(喪失)について
脱退(喪失)の手続き
次のような場合は、その事由が発生した日から14日以内に必ず市役所で手続きしてください。
国保からの脱退は自動では行われません。ご本人あるいは代理人の手続きが必要です。
届出が遅れると、医療費の返還や、五泉市と他保険の保険税を二重に徴収されてしまう場合があります。
| こんなとき | 必要なもの(共通) | 必要なもの(個別) | 対象者が20歳~60歳未満の場合 |
| 市外に転出するとき |
・本人確認書類 ・マイナンバーカードまたは個人番号通知カード |
国保の保険証(転出の手続き後にご案内いたします) | なし |
| 会社の健康保険、または任意継続制度に加入したとき | 勤務先等の保険証、国保の保険証 |
年金手帳または基礎年金番号通知書 |
|
| 生活保護を受けることになったとき | 国保の保険証 | ||
| 65歳~74歳の方で後期高齢者医療制度に加入したとき | 後期高齢者医療制度の保険証、国保の保険証 | なし | |
| 死亡したとき | なし | 国保の保険証 | なし |
※注意※
医療機関を受診される際に、「重度障害者医療費受給者証」などを提示している場合は、一緒にお持ちください。国保の窓口後に担当の課へご案内いたします。
郵便による手続きを希望する場合
平日8:30~17:15に市役所に来庁することが難しい人は、必要書類を市役所へ郵送することで手続きが可能です。
<宛て先>
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
五泉市役所 市民課 保険年金係 行
加入(取得)する場合
・国民健康保険被保険者資格取得届(PDFファイル:440.1KB)
・社会保険等の資格を喪失したことがわかる書類のコピー(資格喪失連絡票、離職票など)
・対象者のマイナンバーがわかるもの
・本人確認書類のコピー(マイナンバーカードなど)
・国民年金被保険者関係報告届(申出)書(PDFファイル:268.5KB)※20歳以上60歳未満の人
脱退(喪失)する場合
・国民健康保険被保険者資格喪失届(PDFファイル:450.4KB)
・社会保険等の保険証のコピー
・国民健康保険被保険者証
・対象者のマイナンバーがわかるもの
・本人確認書類のコピー(マイナンバーカードなど)
ぴったりサービスによる届出
保険証の再発行
保険証を紛失してしまった場合は、再発行いたしますので下記のものを窓口にお持ちください。
【必要なもの】
来庁者の顔写真付きの本人確認書類1点(保険証など顔写真のないものは2点)
別世帯の人が手続きに来庁される場合は、委任状が必要となります。
保険税の算出と納付方法
保険税の納税義務者は世帯主です。
被保険者について算出される「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」、被保険者のうち介護保険第2号被保険者(40~64歳)について算出される「介護納付金分」の合計が保険税となります。
|
医療給付費分 (加入者全員) |
後期高齢者支援金分 (加入者全員) |
介護納付金分 (40歳~64歳) |
|
|---|---|---|---|
| 所得割率 | 8.39% | 2.83% | 2.56% |
| 均等割額 (1人あたり) |
20,800円 | 11,800円 | 13,700円 |
| 平等割額 (1世帯あたり) |
27,100円 | - | - |
| 限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
<保険税の軽減>
その1 所得による判定 (所得がない人は「所得なし」という申告が必要です。正しい軽減判定のために、申告は忘れずにしましょう)
| 区分 | 令和5年中の世帯(被保険者と世帯主)の所得 | |
|
均等割額 平等割額 |
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 5割軽減 | 43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | |
| 2割軽減 | 43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
※給与所得者等・・・一定の給与所得と一定の公的年金等の支給を受ける者
その2 未就学児の均等割半額
未就学児1人に係る均等割額(年額)
| 法定軽減 |
均等割額 (減額前税額) |
未就学児の減額措置 | 課税額 |
| な し | 32,600円 | 16,300円 | 16,300円 |
| 2割軽減世帯 | 26,080円 | 13,040円 | 13,040円 |
| 5割軽減世帯 | 16,300円 | 8,150円 | 8,150円 |
| 7割軽減世帯 | 9,780円 | 4,890円 | 4,890円 |
※均等割額・・・医療給付費分と後期高齢者支援金分の合算
その3 ハローワークから発行される『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』の「離職理由」欄に下表の番号が記載されている人(失業時の年齢が65歳未満)
| 離職理由 | 内容 | 期間 |
| 11 12 21 22 31 32 (特定受給資格者) | 前年中の給与所得を30/100として所得割を算定 | 失業日の翌日~翌年度末 |
| 23 33 34 (特定理由離職者) |
その4 産前産後期間の軽減(所得割額・均等割額)
対象者 令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康保険被保険者
軽減対象期間 単胎妊娠:出産(予定)月の前月から翌々月の4カ月分
多胎妊娠:出産(予定)月の3カ月前から翌々月の6カ月分
出産予定日の6カ月前から届出ができます。
詳しくは下記リーフレットをご覧ください。
〈保険税の減免〉
国保に加入している世帯が、次のいずれかに該当し、保険税を納付することが困難であると認められるときは、申請により保険税の減免を受けられる場合があります。
保険税の減免申請をする場合は、保険税の納期限までに申請してください。
※納期限が到来していない保険税が減免対象となり、納付済みの保険税は除きます。
- 倒産等により廃業、休業、失業、または疾病等により所得が著しく減少した世帯
- 震災、水害、火災等の災害により家屋、家財に著しい被害を受けた世帯
- 災害により主たる所得者が障がい者となった世帯
- 社会保険から後期高齢者医療制度に移行した人の被扶養者を有する世帯
- 収容または拘禁された被保険者を有する世帯
- その他特別な事情により生活が著しく窮迫した世帯
※5については、納期限が到来していても収容または拘禁された期間の保険税が減免対象となります。
<年金から天引きされる人(特別徴収)>
対象者:以下の条件をすべて満たす世帯の世帯主
1.世帯主が国保加入者である。
2.世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満である。
3.世帯主の介護保険料が年金から天引きされている。
4.天引き対象となる年金が18万円以上で、保険税と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えていない。
納期は年6回(下図参照)。
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
| 仮 徴 収 | 本 徴 収 | ||||
|
前年度の保険税額に基づいて 算定された額 |
確定した保険税額から仮徴収分を 差し引いた額 |
||||
<納付書で各自納める人(普通徴収)>
対象者:年金から天引きされる人(特別徴収)以外
納め方:市から送られてくる納付書で、納期限までに納付する
納付場所等:市役所、金融機関、コンビニエンスストア・PayPay・LINEPay(取扱い期限あり)
納期は年9回(下図参照)。納期限は月末です。(12月(6期)は25日となります)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 過年度随時分のみ | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | ||
| 前年中の所得で算定した今年度の年間保険税額 + 過年度随時分 | |||||||||||
○「口座振替」が便利です
納期限にご指定の預金口座から自動的に振り替えて納付されます。
事前申し込みが必要です。(必要なもの:通帳、通帳の届出印)
納めた保険税は、所得税及び住民税の「社会保険料控除」の対象になります。年末調整や確定申告の際は、忘れずに申告してください。
一部負担金(保険医療機関等での負担割合)について
小学校就学前の人:2割負担
小学校就学時から70歳未満の人:3割負担(注釈1)
70歳以上75歳未満の人で現役並み所得者の世帯:3割負担(注釈2)
70歳以上75歳未満の人で現役並み所得者の世帯以外(一般)の人:2割負担
- (注釈1)70歳の誕生日をむかえた人の負担割合が変更になるのは誕生月の翌月となります。
(月の初日生まれの人はその月より負担割合が変更となります) - (注釈2)現役並み所得者とは
70歳以上75歳未満の人で課税所得(市県民税の所得から所得控除を差し引いた額)145万円以上の人及びその人と同一世帯にいる人
ただし、課税所得が145万円以上の人であっても、次に当てはまる人は負担割合は2割となります。
- 同一世帯内の70歳以上75歳未満の被保険者数が1人で収入が383万円未満
- 同一世帯内の70歳以上75歳未満の被保険者数が2人以上で収入額の合計が520万円未満
また、70歳以上の被保険者がいる世帯で、その世帯に属する70歳から74歳の被保険者の、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額の合計が210万円以下の場合は2割負担となります。(申請は不要です。)
療養費
旅行先(海外含む)での急病など、やむを得ない理由で保険証を使わずに治療を受けたとき、または補装具を作ったときなどは、後から必要な書類を添えて申請すると、払い戻しがあります。
入院時食事療養費
入院中の食事の費用は、1食につき460円です。ただし、市民税非課税世帯の人は減額が受けられますので、減額認定証の交付申請をしてください。なお、この費用は、高額療養費の対象になりません。
入院時食事療養費の減額認定証、差額申請のとき、90日以上入院している人は「長期該当者」になりますので、入院日数の確認できるものもお持ちください
高額療養費
病気やケガで診療を受けたときに、支払った自己負担(入院時の食事代は除く)が限度額を超えたとき、申請するとその超えた額が後から払い戻されます。(部屋代など保険のきかない部分は対象外)
基準
- 同じ人が同じ月に同じ医療機関に支払った金額が、自己負担限度額を超えたとき。
- 69歳未満の方で、同じ世帯で同じ月内に21,000円を超える一部負担額の支払いが2回以上ある場合、その合計が自己負担限度額を超えたとき。 (70歳以上の方は一部負担金をすべて合算できます。)
- 血友病や人工透析などの特定疾病の場合は、自己負担額が10,000円(所得状況によっては20,000円)を超えたとき。この場合「特定疾病療養受療証」の交付申請をしてください。
自己負担額の計算は
- 暦月ごと(月の1日から月末まで)
- 同じ医療機関ごと
- 入院と通院、医科と歯科は別
- 入院中の食事代や差額(ベット台は対象外)
出産育児一時金
出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度
国民健康保険に加入している人が出産したとき、医療機関と国民健康保険の世帯主との契約により、出産育児一時金500,000円(または488,000円)を五泉市より医療機関へ直接支払いを行います。
また、医療機関と契約しない場合は、医療機関へ出産費用を支払後、五泉市国保へ出産育児一時金支給申請書の提出をお願いします。
(いずれの場合も他の健康保険から支給される人を除きます。)
産科医療補償制度に加入している病院等での出産は500,000円。その他、制度に加入していない病院等で出産した場合など、488,000円。
出産費貸付制度
国民健康保険に加入している人が出産する場合は、出産費貸付制度をご利用いただくことができます。
限度額
出産育児一時金支給見込額の10分の8
貸付を受けられる人(次のいずれかに該当する人)
(1) 出産予定まで1か月以内の人
(2) 妊娠4か月(12週)以上で、出産に関する費用について病院等に支払いがある人
申請に必要なもの
(1)の場合 : 母子手帳、保険証、振込先口座、印鑑
(2)の場合 : 母子手帳、保険証、振込先口座、印鑑、出産に関する費用の請求書・領収書
社会保険などに加入している人は、加入先の保険にお問い合わせください。
葬祭費
国民健康保険に加入している人が死亡したとき、死亡の原因を問わず、死亡した人が属する世帯の世帯主又は葬祭を行う人に対して50,000円が支給されます。(他の健康保険から支給される人を除く)
他人からけがをさせられたとき
交通事故など第三者(他人)の不法行為によりけがをした場合でも、保険証を使って診療を受けることができます。この場合、届出が義務づけられていますので、必ず窓口に届出をしてください。
交通事故など(第三者の行為)で保険証を利用した場合は届け出が必要となります。
医療費が高額になったとき
保険医療機関に「限度額適用認定証」等を提示することで一定限度額のみの支払になりますので、交付申請をしてください。
関係書類の送付先について
国民健康保険に関する書類は、原則世帯主宛てに送付いたします。
事情があり、別の住所、宛名での送付を希望する場合は、以下の届出が必要です。
国民健康保険関係書類送付先変更届(両面)(PDFファイル:611KB)
裏面の注意事項をよく確認し、添付書類等、不備のないようにお願いします。
マイナ保険証をご利用ください
令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。
マイナ保険証(※)を利用することで、次のようなメリットがあります。(令和6年1月時点)
1.現行の保険証よりも、医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
2.過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
3.限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
※マイナ保険証とは…保険証として利用登録を行ったマイナンバーカードのことです。
マイナンバーカードを保険証として利用するための登録がまだの方は、以下2つの準備をお願いします。
STEP1.マイナンバーカードを申請
主な申請方法
・オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
・郵便による申請
・市役所市民課または村松支所市民係にて申請
STEP2.マイナンバーカードを保険証として登録
利用登録の主な方法
・「マイナポータル」から行う
・ 医療機関または薬局の受付(カードリーダー)で行う
詳しくは、厚生労働省のホームページ(こちら)をご確認ください
デジタル広告:マイナンバーカード「いま」と「これから」
- この記事に関するお問い合わせ先
-
五泉市役所 市民課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417
最終更新日:2020年04月01日